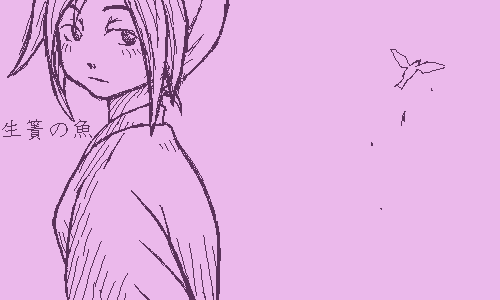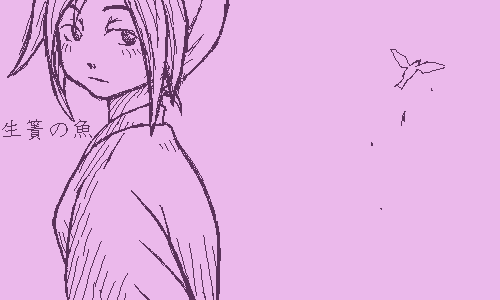
トップへ戻る
生簀の魚
hambato han bart/3253文字/9枚
四の辻にある廓にヤネという遊女がおり、その娘は白波(という名で、母と同じ暮らしをしていた。
白波の小さい頃は他の童と同じく廓の掃除など雑務をこなしていたが、館主(に女として扱われると、ヤネと同じ仕事をするようになった。
娘はまだ少女であるから、どうか勘弁してやって欲しいとヤネは館主に頼んだが、白波には既に客の予約が入っていると断られた。
遊女としての仕事を始めると、白波には母以上の客が寄り付き、少女と、その母親の生活は前より良くなった。
老年の遊女がその少女の身なりを整えると、少女の部屋に迎えられる客の数はさらに増えた。
館主はこれを機にと白波を上(の部屋に格上げさせ、料金を跳ね上げ、特別な扱いとした。
白波がまだ母と同じ棟で暮らしていたある日の事、廓の遊女らにアキツと呼ばれている男を客に迎えた。
アキツは痩せて髪も乱れ、銭の匂いせぬ男と他の女に嫌われている男だった。
男は白波の部屋に入ると、何も面白くないという風情で一直線に中央の座へ向かい、眼下で座っている幼い女を一瞥した。
もの言わぬ男に威圧感と恐怖を覚えつつも、少女は男に、努めて明るくお座り下さいと声を掛けた。
男はしかし聞こえていなかったのか、暫く立って少女を眺め続けていた。
どうかしたのかと少女は男に尋ねた。
返答が無く、代わりに少女は男に押し倒され、これに驚き慄いた。
お侍様、お侍様と少女は男に向かって言ったが、男は侍の召し使いの召し使いだったのでこれに逆上し、少女にいよいよ憎悪と自己嫌悪と孤独と情欲を撒き散らした。
男は肉付きの悪い細身であったが、幼い女より強い力があり、その抵抗をねじ伏せる事が出来た。
未だ数える程しか客を迎えた事はなかったが、いつも客は痩せた男で、いつも客は何も言わず少女を力の支配下に置き、いつも少女はこれを恐ろしく思った。
着物を脱がされる様は暴力そのものだった。
少女は男の顔を見た。
男は少女の顔を見やらず、ただ少女の肢体をのみ見た。
男が少女の内に入り込み、少女は男の顔を見て、泣いた。
母の仕事ぶりを見た時、男性と母は冗談を交し合い町人の話をし、どちらとも口数が減ると布団の方へ向かって行った。
少女は同じものを期待していたが、浅はかな考えであった。
現実には男に組み敷かれているだけだった。
男は蠕動(を休止すると少女をうつ伏せにさせ、再び行為を始めた。
少女は眼をつむり息を止め、身体を強張らせ、館主の犬を思い浮かべた。
犬は少女に獣を見せて、少女はこれが恐ろしくて堪らなかった。
男は少女の尻を打ち続け、遂に果てた。
行為が終わると少女は涙に濡れた目で男を見た。
男は少女を見ると、少し崩れた笑みを浮かべた。
少女も笑顔を作ったが、男はすぐに衣服を整え、少女の部屋を去った。
翌日の朝に白波はその晩の出来事を母に話した。
ヤネは真面目な顔で、殿方との接し方を事細かく娘に話した。
必ず言いつけに従いなさい、と母に厳しい顔で念を押され、白波はそれらを忘れまいと必死に繰り返した。
白波は廓の内に生まれ育ち、死ぬまで外に出る事は無かった。
出たいとか出ようとか思う事も無かった。
白波が特別な部屋で暮らすようになると、母や他の遊女らとの会話は減っていく一方だった。
白波が艶(やかな布を羽織るようになると、ヤネですら少女を疎ましく思ったが、少女にはこれが分からず、ただ自分は他人から興味を失くされたのだと思うようになった。
その頃には白波も仕事に慣れ、無用の心配をする事も少なくなった。
客との付き合い方も分かるようになった。
しかし物事を慣れこなす事は、同時に人同士の繋がりを薄める事にもなった。
年月を経て、少女は室から見える木々や水の流れを眺める時間が多くなっていった。
「私の名はジンウという。きみの名は」
その日、白波の部屋に訪れたのは長身で細長い眼が特徴の男だった。
物腰は柔らかく、服装は整い、穏やかな風情を匂わせていた。
「わちきは白波でありんす」
少女はジンウの声音や表情に親しみを覚えた。
男は白波に色々な事を尋ねた。
その殆どが、一度として他人に聞かれた事のない、取るに足らないものだった。
白波も同様に、ジンウに尋ねられた事を聞き返すなどした。
そのように、気さくに何でも話が出来る相手との出会いは、若い遊女にとって初めての事だった。
しかし白波は無礼を恐れ、慎重に言葉を選び、相手を立て、ジンウの顔色を読み取る事も忘れてはいなかった。
ジンウもこれに気付き、少女の言葉を遮る事無くこれを受け流し、綾取り、少女に対する偽りのない言葉を投げ掛けた。
「きみは美しい。それは、見える何かではなく、聞こえる何かではない」
言葉の先を言葉にせず、ジンウはただ白波を抱擁した。
白波はこの事に痛く心が震えた。
この男に対して、他の者とは違う情が生まれつつあるのを悟った。
しかし男の所作に少しの違和感も覚えた。
男の眼が見据えている先は、どうも白波ではないような気がした。
だがジンウの指先が少女の身体に触れると、多くの雑念は霧散していった。
まるで雀のよう、魚のよう。
ジンウと身を交す事は、水のせせらぎや風のささやきの中に包まれるが如く、白波に陶酔を与えた。
少女には、まるで灯の揺らめきが止まってしまっているようにさえ思えた。
ジンウとの夜は、白波にとって真に特別なものとなった。
翌朝、白波は身支度を整えるジンウに向かい次に会えるのはいつか尋ねた。
ジンウは少し間を置き、白波の年齢を訊いた。少女は十五と答えた。
「では、きみが二十歳になった頃に、再び訪れよう」
男は静かに言った。
少女はその返答の意味を掴みかねたが、再会の約束を素直に喜び、待っていますと強く言った。
ジンウは微かな笑みを見せた。
それから白波は、その約束のみを頼りにして日々を過ごした。
少女にとって五年の歳月は、気の遠くなる程の時間に思えた。
ただ、紅葉と新緑、夏と冬の繰り返しを数えていよう。
あの木だって、そうして生きている。
白波は中庭に佇み、草や虫の中に自らを置いた。
夏の虫が細長く鳴き続けている中、少女は小さく設えられた池を見た。
池の中、大きくもない魚が一匹だけ泳いでいた。
あの魚は、何を待って暮らしているだろう。
少女は一通り考えを巡らせてみたが、どれも楽しいものではなかったので、魚から眼を逸らし空を仰いだ。
ジンウの考えた通り、白波は二十歳を迎えずに流行り病で死んだ。
ヤネが他界した翌日の事で、既に衰弱しきっていた少女は母の死因も知らぬまま静かに息を引き取った。
今際(の際(まで少女はジンウの名を繰り返し呟いた。
他に浮かぶ名が無かった事もあった。
廓の館主は母娘(の死体を近くの山に埋めるよう使いの者に申し付けた。
白波の部屋は、若く愛嬌のある遊女に使われる事となった。
白波は目を覚ますと、見ず知らずの屋敷の内にいた。恐ろしく大きな屋敷だった。
太刀(を佩(き甲冑(を纏(った牛頭(と馬頭(がどこからともなく現われ、少女を奥の室へ促した。
連れられた先にはヤネと閻魔がいた。
庁内と衣装には厳格さが見て取れたが、閻魔そのものはくたびれた老人だった。
ヤネは地獄の王に問答される事無く裁かれ、屈強な閻魔卒(に左の扉へと連れて行かれた。
次に閻魔は白波を見据えた。少女も彼が誰か分かっていた。
王は手元の書物を見ると、顔つきを和らげ、少女に労いの言葉を掛けた。
「自らの由も無く生きたきみの罪を問わず」
閻魔は右の扉を指し、そちらに行くよう述べた。
白波はジンウがどちらに行くのか、或いは行ったのかを尋ねた。
きみの母と同じだと老いた王が言うと、白波も同じ処がいいと言った。
知らぬ処に知る人なく暮らすのは恐ろしいと、少女は必死に訴えた。
閻魔はこれを努めて合理的に説き伏せた。
人としての暮らしはそこに無く、心配は無用だと言うと、少女もそれ以上は主張せず、右の扉へ歩を進めた。
牛頭が扉を開けると、先は光と霧に埋め尽くされて見通せなかった。
少女はこれに警戒感を覚えたが、王の言葉に従い扉の中へと向かった。
こうして白波は、真っ白い煙の中へと消えて去って行った。
生簀の魚/了
トップへ戻る
後書
英題の「ハンバート・ハンバート」とはロリータの語源となった小説(キューブリックが映画にも)「ロリータ」の主人公の名前から。
fiction suckerなら娼婦モノを書かなきゃダメだと思い、少女売春婦の生涯を描いてみたら予想外にも死後の世界まで飛び出て驚いた。
しかし古典文学を愛読する純粋なハートの持ち合わせがあったので見事ハッピーエンドに。
「物語の余分な贅肉はそぎ落とすべき」と思っていたが、やってみたら骨しか残ってなくて喰えねぇって事に気が付いた。いや、豚骨スープにすりゃいいのかな。何の話だ?
描写の量こそが読む人の心に風をそよがせるんだなぁと言うか、結局バランスの取り方を学んで良かったねという事でしょう。